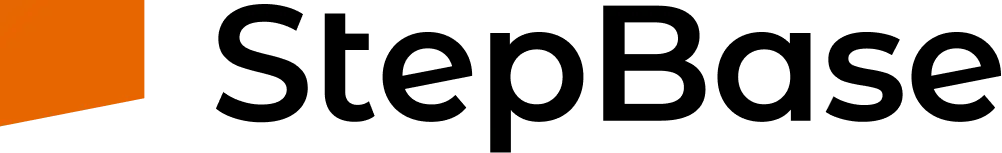給与計算 効率化: リモート・ハイブリッド時代の複雑な手当・控除を自動化し、業務効率を最大化する方法

現代のビジネス環境は、リモートワークやハイブリッド勤務の普及により、劇的な変化を遂げています。柔軟な働き方は従業員の満足度向上や生産性向上に寄与する一方で、企業のバックオフィス、特に給与計算業務には新たな課題をもたらしています。多様化する働き方に伴い、手当や控除の項目は複雑化し、手作業による給与計算は、もはや非効率的であるだけでなく、ヒューマンエラーや法令違反のリスクを増大させています。
本記事では、リモートワーク・ハイブリッド勤務時代における給与計算の課題を深掘りし、複雑な手当や控除を自動化するための具体的な方法、そして自社に最適なソリューションを選ぶためのポイントを解説します。給与計算業務の効率化は、単なるコスト削減に留まらず、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠です。この機会に、貴社の給与計算業務を見直し、未来を見据えた効率化を実現するための一歩を踏み出しましょう。
目次
1.リモート・ハイブリッド勤務がもたらす給与計算の新たな課題

リモートワークやハイブリッド勤務は、従業員に柔軟な働き方を提供する一方で、給与計算業務に特有の複雑さを加えています。従来のオフィス勤務では想定されなかった多様な状況が生まれ、人事・労務担当者はその対応に追われています。
1-1. 勤怠管理の複雑化と労働時間把握の困難さ
オフィス出社と在宅勤務が混在するハイブリッドワークでは、従業員の労働時間を正確に把握することが一層困難になります。例えば、週のうち数日はオフィスに出社し、残りは在宅で勤務するといった働き方では、タイムカードや日報による従来の勤怠管理では、打刻忘れや申請漏れが発生しやすくなります。
また、フレックスタイム制や裁量労働制など、多様な働き方を導入している企業では、それぞれの勤務形態に合わせた労働時間の集計が必要となり、複雑性が増します。テレワーク中の従業員が本当に勤務しているのか、労働状況の把握も課題となることがあります。
1-2. 手当・控除項目の多様化と計算ロジックの複雑化
リモートワークの導入に伴い、新たな手当や控除項目が発生しています。例えば、通勤手当の実費精算や、在宅勤務手当、通信費補助などがその代表例です。これらの手当は、オフィス出社の有無や頻度によって支給額が変動することが多く、個別に対応する必要が生じます。
加えて、地域手当、役職手当、住宅手当、時間外手当など、既存の複雑な手当の計算ロジックも、リモート環境下での勤務実態に合わせて見直す必要があり、計算がさらに複雑化します。社会保険料や所得税、住民税といった控除項目も、法改正によって料率や計算方法が頻繁に変更されるため、常に最新の情報を反映させる手間がかかります。
1-3. 情報連携・データ管理の非効率性
リモートワークでは、紙ベースでの資料管理やデータの共有が困難になります。勤怠データ、人事異動情報、各種申請書類などが複数のシステムやファイルに散在している場合、給与計算のためにそれらのデータを手作業で収集・入力・照合する作業は膨大な時間と手間を要します。
また、担当者個人のスキルや経験に依存する「属人化」が進むと、担当者の異動や退職時に業務が滞るリスクも高まります。データの正確性が損なわれるだけでなく、情報漏洩のリスクも無視できません。
1-4. 法改正への対応負担
給与計算は、労働基準法、所得税法、社会保険関連法規など、多岐にわたる法令に厳密に準拠する必要があります。これらの法令は頻繁に改正され、例えば社会保険料率の変更や、育児休業給付金制度の改正など、常に最新の情報にアップデートし、正確に給与計算に反映させなければなりません。自社でこれらの法改正に迅速かつ適切に対応するには、常に専門知識を習得し続ける必要があり、担当者にとって大きな負担となります。
2.なぜ今、「給与計算の効率化」が不可欠なのか?

給与計算業務の効率化は、単なる手間の削減に留まらず、企業経営に多大なメリットをもたらします。一方で、導入にあたっては考慮すべき点も存在します。
2-1. 給与計算効率化のメリット
給与計算を自動化・効率化することには、以下のような多くのメリットがあります。
| 業務負担の軽減と時間の創出 | 従業員の数が増えれば増えるほど、毎月の給与計算の作業は大きくなりますが、自動化によって大幅に工程を減らし、担当者の負担を軽減できます。これにより、担当者は他の戦略的な業務や、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。 |
|
ヒューマンエラーの防止と 正確性の向上 |
手作業やExcelでの管理では、どんなに注意しても入力ミスや計算ミスが発生するリスクが伴います。給与計算システムを導入すれば、あらかじめ設定された計算ロジックに基づいて自動で処理されるため、人為的な計算ミスを軽減し、正確性を担保できます。これにより、従業員からの信頼を損なう事態や再計算の手間も回避できます。 |
| 法令遵守とリスク回避 | 給与計算は法改正の影響を大きく受ける業務であり、最新の法令に対応することは企業の義務です。給与計算システムは、社会保険料率や税制の変更など、法改正に自動で対応するため、法令遵守が容易になり、法的なリスクを回避できます。 |
| 人件費の削減とコスト最適化 | 給与計算の自動化により、計算に関わる業務時間が減れば、その分の人件費削減も期待できます。また、紙の給与明細の発行・封入・郵送にかかるコストや手間も削減でき、ペーパーレス化を促進できます。 |
| 属人化の解消と業務の標準化 | システム導入により、給与計算のプロセスが標準化され、特定の担当者に業務が集中する属人化を解消できます。これにより、担当者の急な欠勤や異動時でも、スムーズに業務を継続できるようになります。 |
| 従業員満足度の向上 | 正確で迅速な給与支給は、従業員の企業への信頼感を高めます。また、Web給与明細の導入により、従業員はいつでもどこでも自身の給与情報を確認できるようになり、利便性が向上します。 |
2-2. 給与計算効率化のデメリット・注意点
メリットが多い一方で、効率化には以下のような注意点もあります。
| 導入・運用コストの発生 | 給与計算システムやアウトソーシングの導入には、初期費用や月額のランニングコストがかかります。自社の規模や必要な機能に見合った投資であるか、費用対効果を慎重に検討する必要があります。 |
| システム選定と初期設定の手間 | 自社に最適なシステムを選ぶためには、複数の製品を比較検討し、自社の給与体系や就業規則に合わせて初期設定を行う手間が発生します。このプロセスを怠ると、導入後に期待通りの効果が得られない可能性があります。 |
| セキュリティ面での懸念 | 給与データには個人情報やマイナンバーなど機密性の高い情報が含まれます。クラウドサービスを利用する場合、インターネットを介してデータが扱われるため、ウイルス感染やハッキングによる情報漏洩のリスクはゼロではありません。導入するシステムのセキュリティ体制を十分に確認することが重要です。 |
| カスタマイズ性の限界 | 市販の給与計算ソフトやサービスは、一般的な給与体系には対応していますが、インセンティブが多く複雑な計算が必要な場合や、独自の細かいルールを持つ企業では、システムに合わせるための追加処理が必要になったり、対応できない場合があります。 |
| 業務フローがシステムに依存 | システムを導入すると、給与計算の業務フローがシステムに依存するようになります。万が一システム障害が発生した場合や、システムの変更が必要になった場合に、業務に支障が出る可能性があります。 |
3.複雑な手当や控除を自動化する具体的な方法

給与計算の複雑さを解消し、効率化を図るためには、主に「給与計算システムの導入」「HRISとの連携」「RPA/AIの活用」「給与計算アウトソーシング」の4つの方法が考えられます。
3-1. 給与計算システムの導入
給与計算システムは、従業員の基本給や各種手当、残業代、控除額などを自動で計算する専門のソフトウェアです。
主な機能としては、以下が挙げられます。
| 自動計算機能 | 基本給だけでなく、時間外手当、休日出勤手当、深夜労働手当などの割増賃金、役職手当、通勤手当といった各種手当、さらに健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料、所得税、住民税などの控除額を自動で正確に計算します。従業員情報や就業規則に沿った設定をしておけば、複雑な計算も自動で行われます。 |
| Web給与明細の発行 | システムが計算を完了すると同時に、支給項目と控除項目が記載された給与明細書を自動で作成し、Web上で従業員に配布できます。これにより、印刷や封入、配布といった物理的な手間やコストを削減できます。 |
| 年末調整・社会保険手続きのサポート | 年末調整のためのデータ作成や申告書作成をサポートし、社会保険料の月額変更など、年に一度の煩雑な手続きを簡易化できるシステムもあります。 |
提供形態は、インターネット環境があればどこからでも利用できる「クラウド型」と、自社サーバーにインストールして利用する「オンプレミス型」に大別されます。リモートワーク環境においては、場所を選ばずアクセスできるクラウド型が特に有効です。
3-2. HRIS(人事情報システム)との連携
給与計算の効率を最大限に引き出すためには、給与計算システム単体だけでなく、人事情報システム(HRIS)全体との連携が不可欠です。
| 勤怠管理システムとの連携 | 給与計算の土台となる勤怠データは、労働時間や残業時間、有給休暇の取得状況など、多岐にわたります。勤怠管理システムと給与計算システムを連携させることで、従業員の打刻データを自動で取り込み、集計作業の手間を大幅に削減できます。これにより、手入力によるミスを防ぎ、正確な給与計算を担保できます。 |
| 人事マスタ情報との自動連携 | 昇給、異動、退職などに伴う給与体系の変更は、給与計算に直接影響します。HRISで管理されている人事マスタ情報(基本給、役職、各種手当の有無など)と給与計算システムを連携させることで、これらの情報変更が自動的に給与計算に反映され、設定漏れや更新忘れを防ぐことができます。 |
| 会計システムとの連携 | 給与計算の結果は、人件費として会計処理に反映されます。給与計算システムと会計システムを連携させることで、人件費に関する仕訳データを自動で作成し、経理業務の効率化にも繋がります。 |
3-3. RPA/AIの活用
RPA(Robotic Process Automation)やAI(人工知能)の技術は、給与計算業務のさらなる自動化を可能にします。
| 定型業務の自動化 | RPAは、勤怠データの集計、各種申請書類の確認、給与データ入力、異なるシステム間のデータ転記など、反復的でルールに基づいた定型業務を自動化します。これにより、担当者の手作業を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクを低減できます。 |
|
AIによる複雑なデータ処理・予測分析 |
AIは、RPAでは難しい複雑なデータ処理や、過去のデータに基づいた予測分析を可能にします。将来的には、複雑な手当の計算ロジックの最適化や、法令改正の予測、人件費のシミュレーションなどに応用される可能性も秘めています。例えば、OCR(光学文字認識)とAIを組み合わせることで、紙の書類からのデータ入力も自動化できるでしょう。 |
3-4. 給与計算アウトソーシング
自社でシステム導入や運用が難しい場合、給与計算業務そのものを外部の専門業者に委託する「給与計算アウトソーシング」も有効な選択肢です。
| 専門知識の活用 | アウトソーシング企業は、給与計算に関する専門知識を持つプロフェッショナルであり、労働法、税法、社会保険法など、頻繁に改正される法令に常に迅速かつ正確に対応してくれます。これにより、自社で専門知識を維持・更新する負担を軽減し、法令遵守を強化できます。 |
| コスト削減とコア業務への集中 | 自社で給与計算担当者を雇用・育成する人件費や、給与計算ソフトの導入・維持管理費、給与明細の印刷・郵送費などを削減できます。給与計算というノンコア業務を外部に委託することで、企業は本来注力すべき経営戦略やコア業務にリソースを集中させることができます。 |
| セキュリティ強化 | 信頼できるアウトソーシング業者を選べば、厳重なセキュリティ体制の下で個人情報が管理されるため、自社でセキュリティ対策を行うよりも情報漏洩リスクを低減できる場合があります。 |
| 柔軟な運用 | 企業の規模拡大や組織変更に伴い、給与計算業務の内容も変化しますが、アウトソーシングサービスはこうした変化に柔軟に対応できるため、ビジネス環境の変化に適応しやすいという特徴があります。 |
ただし、委託範囲や料金体系は業者によって異なるため、自社のニーズを明確にし、費用対効果を十分に検討することが重要です。
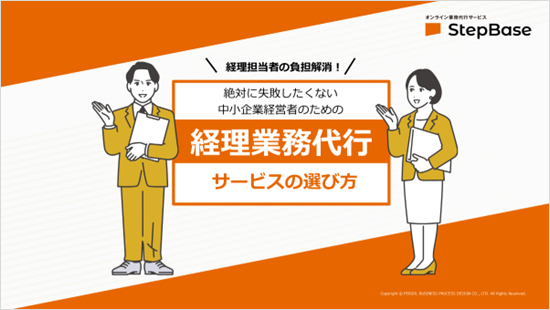
絶対失敗したくない方必見!経理業務代行サービスの選び方
|
・雑務でコア業務に集中できない… |
4.自社に最適な「給与計算 効率化」ソリューションを選ぶポイント

給与計算の効率化を実現するためには、自社の現状と将来の展望に合致した最適なソリューションを選ぶことが重要です。以下のポイントを参考に、慎重に検討を進めましょう。
4-1. 目的の明確化
まず、給与計算の効率化を通じて何を達成したいのか、具体的な目的を明確にしましょう。例えば、「月次の給与計算にかかる時間を10時間削減したい」「計算ミスをゼロにしたい」「法改正への対応漏れリスクを減らしたい」「Web給与明細を導入してペーパーレス化を進めたい」といった具体的な目標を設定することで、必要な機能やサービスが見えてきます。
4-2. 機能の網羅性と柔軟性
自社の給与体系や就業規則、従業員の働き方に、システムがどこまで対応できるかを確認します。
| 複雑な手当・控除への対応 | リモートワーク手当、通勤手当の変動、役職手当、住宅手当など、自社特有の複雑な手当や控除を柔軟に設定・計算できるかを確認しましょう。変形労働時間制やフレックスタイム制など、多様な勤務形態に対応しているかも重要です。 |
| 必要な機能の有無 | 勤怠管理、年末調整、社会保険手続き、Web給与明細発行など、自社が効率化したい業務に必要な機能が網羅されているかを確認します。 |
4-3. 既存システムとの連携性
すでに導入している勤怠管理システム、人事情報システム(HRIS)、会計システムなどとスムーズに連携できるかは、給与計算業務全体の効率を大きく左右します。データの自動連携によって、手入力や二重入力の手間とミスを削減できます。
4-4. セキュリティ体制
給与データは機密性の高い個人情報を含むため、セキュリティ対策は最も重要な選定基準の一つです。
| 情報漏洩対策 | データの暗号化、アクセス制限、脆弱性診断、バックアップ体制など、どのようなセキュリティ対策が講じられているかを確認します。 |
| プライバシーマークやISMS認証 | 外部認証の有無も、セキュリティ信頼性の一つの指標となります。 |
4-5. サポート体制
システム導入時だけでなく、運用開始後のトラブル対応や法改正へのアップデート、操作方法に関する問い合わせなど、充実したサポート体制が提供されているかを確認しましょう。特に、法改正への対応力は、給与計算業務の正確性を維持するために不可欠です。
4-6. 費用対効果
導入コスト、月額利用料、オプション料金など、総費用を把握し、それによって得られる業務削減効果やリスク低減効果と見合っているかを検討します。単に費用が安いだけでなく、長期的な視点で最もコストパフォーマンスが高いソリューションを選ぶことが重要です。
4-7. 操作性・使いやすさ
システムを利用する人事・労務担当者だけでなく、勤怠入力を行う従業員、承認を行う管理者など、関係者全員にとって操作が直感的で分かりやすいシステムを選ぶことが、スムーズな導入と定着の鍵となります。無料トライアルなどを活用し、実際に使用感を確かめるのも良い方法です。
5.給与計算効率化の成功事例

ここでは、給与計算の効率化に成功した企業の事例をいくつかご紹介します。
事例1. 勤怠システムと給与計算システムの連携で月次業務を短縮
ある中小企業では、リモートワーク導入により、従業員それぞれの勤務状況が複雑化し、勤怠集計と給与計算に毎月多くの時間を費やしていました。そこで、クラウド型の勤怠管理システムと給与計算システムを連携させた結果、勤怠データが自動で給与計算システムに取り込まれるようになり、月次業務の締め日を5日短縮することに成功しました。これにより、担当者の残業時間が削減され、ヒューマンエラーも大幅に減少しました。
事例2. Web給与明細導入によるペーパーレス化とコスト削減
従業員数が多く、紙の給与明細の発行・配布に多大なコストと手間がかかっていた企業では、Web給与明細機能を備えた給与計算システムを導入しました。これにより、給与明細の印刷、封入、郵送にかかる費用がゼロになっただけでなく、配布作業にかかる担当者の工数も大幅に削減され、年間で数十万円規模のコストカットを実現しました。従業員もスマートフォンからいつでも給与明細を確認できるようになり、利便性が向上しました。
まとめ:給与計算の効率化で未来を拓く
リモートワークやハイブリッド勤務が常態化する現代において、給与計算業務の複雑化は避けられない課題です。しかし、給与計算の効率化は、単なる業務負担の軽減に留まらず、ヒューマンエラーの防止、法令遵守の強化、人件費の削減、そして担当者がコア業務に集中できる環境を整えるなど、企業経営に多岐にわたるメリットをもたらします。
給与計算システムやHRISとの連携、RPA/AIの活用、給与計算アウトソーシングといった多様なソリューションを適切に組み合わせることで、複雑な手当や控除も自動化し、給与計算業務の品質と効率を飛躍的に向上させることが可能です。自社の現状と将来のビジョンを見据え、最適なソリューションを選定することが、持続的な成長を遂げるための重要なステップとなります。
「給与計算の効率化」に関するお悩みや、最適なソリューションの選定でお困りでしたら、ぜひStepBaseにご相談ください。長年の経験と専門知識を持つプロフェッショナルが、貴社の状況に合わせた最適なバックオフィスサポートをご提案し、業務効率化の実現を強力に支援いたします。
>>給与計算を含むバックオフィス業務の効率化について、今すぐStepBaseに相談する
▼ StepBase経理のサービス詳細はこちらから
https://step-base.jp/accounting/
経理業務の人材不足・業務効率化にお悩みなら
「StepBase」にご相談ください!
|
パーソルグループの
|
✔ 経験豊富なプロが業務を代行 ✔ 10時間/3.9万円からスタートできる ✔ 月末月初の業務過多に素早く対応! |