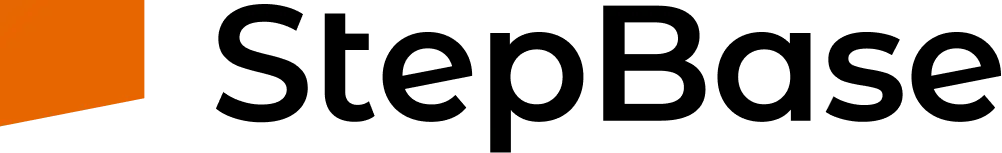給与計算の基本の「き」:初めての担当者が押さえるべき8つのステップ

企業経営において、従業員への給与支払いは最も重要かつデリケートな業務の一つです。特に初めて給与計算を担当する方にとっては、「何から手をつければ良いのか」「ミスなく正確に行うにはどうしたら良いのか」といった不安を抱くことも少なくないでしょう。給与計算は、単にお金を支払うだけでなく、労働基準法や税法、社会保険法といった多岐にわたる法令遵守が求められる専門性の高い業務だからです。
本記事では、初めて給与計算を担当する方が自信を持って業務に取り組めるよう、給与計算の基礎知識から具体的な8つのステップ、さらにはよくある間違いと対策、効率化の方法までを網羅的に解説します。この記事を通じて、給与計算業務の全体像を理解し、正確でスムーズな処理を実現するための実践的なヒントを習得してください。
【関連記事】経理 業務効率化:ムダをなくす!今日からできる具体的な5つのステップ
目次
1. 給与計算とは?なぜ重要なのか

給与計算とは、従業員の労働に対する対価である「総支給額」から、法律で定められた「法定控除額」や企業が独自に定める「法定外控除額」を差し引き、最終的に従業員に支払われる「差引支給額(手取り額)」を算出する一連の業務を指します。
この業務は、企業の運営において極めて重要な意味を持ちます。
| 従業員の生活基盤の維持 | 従業員の生活を支える給与を正確かつ期日通りに支払うことは、雇用主として最低限の義務です。 |
| 法令遵守 | 労働基準法、所得税法、社会保険法など、給与計算に関わる法律は多岐にわたり、一つでも違反すれば企業の信用失墜や罰則、訴訟のリスクを招きます。 |
| 企業と従業員の信頼関係構築 | 正確で透明性のある給与計算は、従業員の企業に対する信頼感を高め、安心して仕事に取り組める環境を醸成します。 |
給与計算は、単なる数字の計算ではなく、企業のコンプライアンスと従業員エンゲージメントを支える重要なバックオフィス業務なのです。
2. 初めての給与計算担当者が直面する課題

給与計算の重要性は理解しつつも、初めて担当する際には以下のような課題に直面しがちです。
| 専門知識の広範さ | 労働基準法、社会保険法、所得税法、住民税法など、関連する法律や制度が広範囲に及び、常に最新情報をキャッチアップする必要があります。 |
| 計算の複雑性 | 基本給だけでなく、各種手当、残業代、社会保険料、税金など、従業員一人ひとりの状況に応じて計算項目が多岐にわたるため、複雑な計算が求められます。特に、割増賃金の計算や社会保険料・税金の料率は法改正によって変動することがあります。 |
| ミスが許されないプレッシャー | わずかな計算ミスや知識不足が、従業員からの不信感、未払い賃金トラブル、税務調査での指摘など、企業に大きなリスクをもたらす可能性があります。 |
| 業務の属人化リスク | 専門性が高いゆえに、特定の担当者しか業務内容を把握していない「属人化」が起こりやすく、担当者の不在時に業務が滞るリスクがあります。 |
これらの課題を乗り越え、正確かつ効率的に給与計算を行うためには、体系的な知識と手順の理解が不可欠です。
3. 給与計算の基本の「き」:初めての担当者が押さえるべき8つのステップ

給与計算は、大きく分けると「総支給額の算出」「控除額の算出」「差引支給額の算出」という3つのステップで構成されます。 ここでは、これらの主要なステップをさらに細分化し、初めての担当者が着実に進められる8つのステップとして解説します。
step1. 勤怠情報の収集と確認
給与計算の最初のステップは、従業員の正確な勤怠情報を収集し、確認することです。これがすべての計算の基礎となります。
✅収集する情報
|
✅準備するもの
|
勤怠情報は、総支給額を正確に算出するために最も重要な要素です。集計ミスがないよう、複数回確認するなどの対策を講じましょう。
step2. 総支給額の算出
次に、ステップ1で収集した勤怠情報をもとに、従業員に支給されるすべての金額(総支給額)を計算します。
✅内訳
| 基本給 | 雇用契約や就業規則で定められた基本的な賃金。 |
| 各種手当 | 通勤手当、住宅手当、役職手当、家族手当、資格手当など、企業が独自に定める手当。 |
| 割増賃金 |
時間外手当(残業手当) 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働した場合に発生。割増率は原則25%以上。 |
|
深夜手当 午後10時から午前5時までの間に労働した場合に発生。割増率は原則25%以上。 |
|
|
休日手当 法定休日(週1日または4週4日)に労働した場合に発生。割増率は原則35%以上。 |
✅計算方法
| 総支給額 = 基本給 + 各種手当 + 割増賃金 |
特に割増賃金については、労働基準法で定められた計算方法と割増率を正確に適用することが重要です。
step3. 法定控除額の算出
総支給額が算出できたら、従業員の給与から差し引かれる「法定控除額」を計算します。法定控除は法律で義務付けられているため、すべての従業員の給与から控除する必要があります。
✅法定控除の種類
社会保険料
健康保険料、介護保険料(40歳以上65歳未満の従業員)、厚生年金保険料、雇用保険料の4種類。
| 計算方法 |
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料 従業員の「標準報酬月額」に各保険の「保険料率」を掛けて算出します。 標準報酬月額は、給与を一定の幅で区切った等級に当てはめて決定されます。 保険料率は、健康保険は都道府県や加入している健康保険組合によって異なり、毎年改定されることがあります。 |
|
雇用保険料 従業員の「賃金総額」に「雇用保険料率」を掛けて算出します。 雇用保険料率も業種によって異なり、毎年見直されることがあります。 |
|
| 注意点 |
社会保険料は会社と従業員が折半して負担します。 また、原則として「翌月徴収」が行われます。 |
所得税(源泉徴収税)
国に納める税金で、毎月の給与から概算額が「源泉徴収」されます。
| 計算方法 | 「給与所得の源泉徴収税額表」を使い、社会保険料控除後の給与額と扶養親族等の数に応じて税額を算出します。 |
| 注意点 | 年末調整で年間所得税額が確定し、過不足が調整されます。 |
住民税
都道府県と市区町村に納める地方税です。前年の所得に基づいて計算され、各自治体から企業に通知されます。
| 計算方法 | 所得割(所得に応じて課税)と均等割(地域住民に一律課税)の合算で、通知された年税額を12ヶ月で割って毎月徴収します。 |
| 注意点 | 毎年5月〜6月頃に新しい通知書が届き、その年の6月以降の給与から新しい税額が適用されます。 転職や退職の際には特別な処理が必要です。 |
✅準備するもの
|
step4. その他の控除額の算出(法定外控除)
法定控除以外にも、企業と従業員の間で合意があれば、給与から控除できる項目があります。これらを「法定外控除(協定控除)」と呼びます。
例 |
財形貯蓄、社内預金、労働組合費、社員旅行の積立金、互助会費、寮費、社宅費など。 |
|
注意点 |
これらの控除を行うには、労働組合がある場合は労働組合と、ない場合は従業員の過半数を代表する者との間で「労使協定」を締結し、給与から控除する旨を明記する必要があります。 |
step5. 差引支給額(手取り)の算出
いよいよ従業員に実際に支払われる「差引支給額」、いわゆる「手取り額」を算出します。
✅計算方法
| 差引支給額 = 総支給額 − 法定控除額 − その他の控除額 |
この計算結果が、従業員の銀行口座に振り込まれる金額となります。
step6. 給与明細書の発行
給与計算が完了したら、従業員一人ひとりに給与明細書を発行します。給与明細書には、総支給額の内訳、各控除額、そして差引支給額を明示する必要があります。
✅発行方法
|
Web明細は、ペーパーレス化や配布の手間削減に貢献するため、多くの企業で導入が進んでいます。
step7. 給与の支払い
計算された差引支給額を、決められた期日までに従業員へ支払います。
✅賃金支払いの5原則
労働基準法第24条では、賃金の支払いについて以下の5原則を定めています。
| 通貨払いの原則 | 現金で支払う(例外として、労使協定があれば銀行振込も可)。 |
| 直接払いの原則 | 従業員本人に直接支払う。 |
| 全額払いの原則 | 法定控除以外の控除は労使協定が必要。 |
| 毎月1回以上払いの原則 | 最低でも月に1回は支払う。 |
| 一定期日払いの原則 | 毎月同じ期日に支払う。 |
現代では銀行振込が一般的ですが、賃金支払いの5原則は給与計算の基本として常に意識しておく必要があります。
step8. 関連書類の保管と提出(年末調整・社会保険手続きなど)
給与計算業務は、給与の支払いをもって終わりではありません。関連する書類の保管や、定期的な行政機関への提出業務も重要です。
✅主な業務
| 賃金台帳の作成・保管 | 従業員ごとの給与支払状況を記録したもので、法律で作成・保管が義務付けられています。 |
| 源泉徴収票の発行 | 従業員が年末調整や確定申告を行う際に必要となる書類です。 |
| 社会保険関連の届出 | 従業員の入退社時や、年に一度の定時決定(算定基礎届)など、社会保険に関する様々な届出が必要です。 |
| 年末調整の実施 | 毎年11月から12月にかけて行う、年間の所得税の過不足を調整する重要な手続きです。 従業員から扶養控除等申告書などの書類を回収し、1年間の給与収入から所得控除等を差し引いて課税所得を計算し、所得税額を確定させます。 |
これらの書類管理や手続きも、給与計算担当者の重要な役割です。
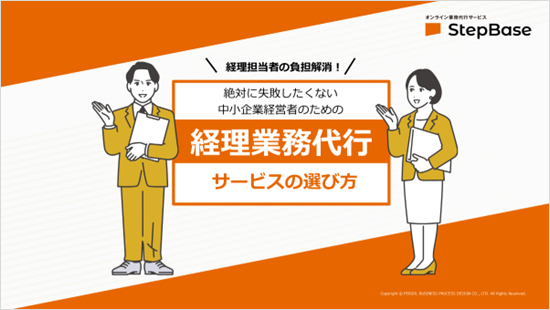
絶対失敗したくない方必見!経理業務代行サービスの選び方
|
・雑務でコア業務に集中できない… |
4. 給与計算でよくある間違いと対策

給与計算はミスが許されない業務ですが、人間の手作業には常にエラーのリスクが伴います。ここでは、給与計算でよくある間違いとその対策を紹介します。
4-1.よくある間違い
| 勤怠集計のミス | 打刻漏れの見落とし、時間外労働時間の集計ミスなど。 |
| 割増賃金の計算ミス | 残業代や深夜手当、休日手当の割増率の適用間違いや、1時間あたりの賃金の算出ミス。 |
| 社会保険料率・税額の適用ミス | 毎年改定される保険料率や税額への対応漏れ、従業員の年齢(介護保険料の有無)や扶養家族の変更反映漏れ。 |
| 各種手当の反映漏れ | 役職手当や資格手当など、従業員や時期によって変動する手当の反映漏れ。 |
| 月途中退職者の社会保険料控除ミス | 月の途中で退職した場合の社会保険料の控除有無は、退職日によって異なります。 |
| 源泉徴収税額表の適用ミス | 扶養親族の数の間違いや、甲欄・乙欄の適用ミス。 |
4-2.ミスが引き起こすリスク
| 従業員の信頼喪失 | 給与は従業員の生活に直結するため、ミスは大きな不信感につながります。 |
| 法的リスク | 未払い賃金は労働基準法違反となり、是正勧告、罰則、さらには訴訟に発展する可能性があります。 過払いの場合も、返還交渉が難しいケースがあります。 |
| 税務リスク | 所得税や住民税の計算ミスは、税務調査での指摘や追徴課税につながることがあります。 |
| 情報漏洩のリスク | 給与情報は個人情報の中でも特に機密性が高く、取り扱いミスは重大な情報漏洩事故につながります。 |
4-3.ミスをなくすための対策
| ダブルチェック体制の構築 | 担当者だけでなく、必ず別の上長や同僚がチェックする体制を構築しましょう。 |
| 給与計算ソフトの導入 | 複雑な計算や法改正への対応を自動化し、ヒューマンエラーのリスクを大幅に軽減できます。 |
| 年間スケジュールの作成 | 保険料率や税額の改定時期、年末調整のスケジュールなどを一覧化し、事前に準備できるようにします。 |
| 法令・制度の最新情報キャッチアップ | 国税庁や厚生労働省のウェブサイト、専門誌などで常に最新情報を確認する習慣をつけましょう。 |
| 就業規則・給与規定の確認 | 自社の規定を熟知し、変更があった際は速やかに給与計算に反映させましょう。 |
5. 給与計算を効率化するツールやサービス

給与計算業務の複雑さとミスのリスクを考えると、効率化は必須課題です。ここでは、業務効率化に役立つツールやサービスを紹介します。
【関連記事】経理 業務効率化:ムダをなくす!今日からできる具体的な5つのステップ
5-1.給与計算ソフト
多くの企業で導入されているのが給与計算ソフトです。
| 自動計算 | 基本給、手当、残業代、社会保険料、税金などを自動で計算し、計算ミスを削減します。 |
| 法改正への自動対応 | 保険料率や税額の変更などが自動でシステムに反映されるため、手作業での更新漏れを防げます。 |
| Web明細発行 | 紙の明細書を印刷・封入・配布する手間がなくなり、コスト削減とペーパーレス化に貢献します。 |
| 他システムとの連携 | 勤怠管理システムや人事労務システム、会計システムと連携することで、データ入力の手間を省き、業務全体を効率化できます。 |
給与計算ソフトには、クラウド型とインストール型があり、企業の規模や予算、求める機能に応じて多様な製品が提供されています。
5-2.勤怠管理システム
給与計算の元となる勤怠情報を正確に収集するために、勤怠管理システムも有効です。
| 打刻データの自動集計 | 従業員の出退勤時刻を自動で記録・集計し、手作業による転記ミスを防ぎます。 |
| 残業時間・休日出勤時間の自動計算 | 複雑な割増賃金の計算に必要な時間を自動で算出し、給与計算ソフトとの連携でさらに効率化できます。 |
6. アウトソーシングという選択肢

給与計算の専門性や煩雑さ、ミスのリスクを考慮すると、業務の一部または全部を外部の専門業者に委託する「アウトソーシング」も有力な選択肢となります。
6-1.アウトソーシングのメリット
| コア業務への集中 | 給与計算業務にかかる時間と労力を削減し、人事・総務部門が本来注力すべき採用活動や人材育成などのコア業務に集中できます。 |
| コスト削減 | 専門人材の採用・育成コスト、給与計算ソフトの導入・維持コスト、紙媒体の印刷・郵送コストなどを削減できる可能性があります。 |
|
専門知識の活用と 法改正へのスムーズな対応 |
税理士事務所や社会保険労務士事務所、または給与計算専門のアウトソーシング会社は、常に最新の法令知識を持っており、法改正にも迅速かつ正確に対応してくれます。 |
| 業務の属人化の解消とミスの防止 | 特定の従業員への依存リスクを回避し、専門家によるダブルチェック体制で計算ミスを防ぎます。 |
| セキュリティ強化 | 機密性の高い給与情報を外部の専門業者に委託することで、情報漏洩のリスクを軽減できる場合があります。 |
6-2.委託できる業務範囲
アウトソーシングで委託できる業務は多岐にわたります。
|
どの範囲までを委託するかは、自社の課題や予算に応じて検討することが重要です。
給与計算業務は、複雑な法令知識と正確性が求められるため、初めての担当者にとっては大きな負担となりがちです。もし、これらの業務に不安を感じる、あるいはコア業務に集中したいとお考えであれば、専門性の高いオンラインアシスタントサービス「StepBase」をご検討ください。StepBaseでは、給与計算を含むバックオフィス業務全般を、経験豊富なプロフェッショナルがサポートいたします。
まとめ
本記事では、初めて給与計算を担当する方に向けて、給与計算の基本から具体的な8つのステップ、よくある間違いとその対策、そして効率化の手段としてのツールやアウトソーシングについて詳しく解説しました。
給与計算は、従業員の生活と企業の法令遵守を支える非常に重要な業務です。複雑で専門的な知識が求められますが、正しい手順と知識を身につけ、適切なツールやサービスの活用を検討することで、ミスなく正確に、そして効率的に進めることが可能です。
StepBaseでは、経理業務の効率化に関するご相談や、最適なアウトソーシング手法をご提案しています。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。課題解決をサポートし、スムーズな業務変革を強力に推進いたします。
▼ StepBase経理のサービス詳細はこちらから
https://step-base.jp/accounting/
▼ 【お役立ち資料】経理代行ガイドもぜひご確認ください
経理業務の人材不足・業務効率化にお悩みなら
「StepBase」にご相談ください!
|
パーソルグループの
|
✔ 経験豊富なプロが業務を代行 ✔ 10時間/3.9万円からスタートできる ✔ 月末月初の業務過多に素早く対応! |