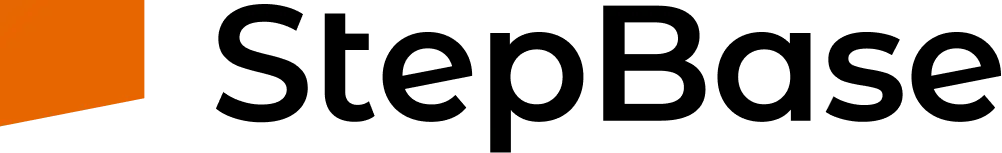経理の人手不足を解消する!効率的な業務フロー構築術とDX推進

深刻化する経理部門の人手不足問題
近年、多くの企業で事業活動の根幹を支える経理部門において、人手不足が深刻な課題となっています。少子高齢化による労働人口の減少、採用難、そして働き方改革への対応など、複合的な要因が絡み合い、経理担当者の確保は一層困難を極めています。この人手不足は、単に業務が滞るだけでなく、従業員の過重労働による離職、ミスの増加、ひいては企業の経営判断にも悪影響を及しかねません。
しかし、この難局を乗り越えるための道筋は確かに存在します。それは、目の前の業務をただこなすのではなく、根本から「業務フローを見直し、効率化を図る」ことです。本記事では、経理のプロの視点から、人手不足の根本原因を深掘りし、その解消に向けて実践すべき効率的な業務フロー構築術を徹底解説します。属人化の排除からITツールの活用、そしてアウトソーシングの戦略的な導入まで、具体的なステップと実践的なアドバイスを通じて、貴社の経理部門が持続的に成長できる体制を構築するためのヒントを提供します。
この記事を最後までお読みいただくことで、経理部門が抱える人手不足の問題を解消し、より生産的で戦略的な部門へと進化するための具体的な道筋が見えてくるでしょう。
目次
1.なぜ経理部門で人手不足が深刻化するのか?

経理部門における人手不足は、一朝一夕に生じたものではありません。複数の要因が複雑に絡み合い、慢性的な問題として企業に重くのしかかっています。ここでは、その主な原因を深掘りします。
1-1. 少子高齢化と採用難による労働人口の減少
日本全体の構造的な問題として、少子高齢化による労働人口の減少が挙げられます。特に経理職は専門性が求められるため、経験者の採用は一層困難です。有効求人倍率は高い水準で推移しており、企業間で優秀な人材の獲得競争が激化しています。経理人材の確保は、単に人数を増やすだけでなく、スキルと経験を兼ね備えた質の高い人材をいかに獲得するかが課題となっています。
1-2. 経理業務の複雑化・専門化と法改正への対応
税法、会社法、会計基準などの頻繁な改正は、経理業務の複雑性を一層高めています。IFRS(国際会計基準)への対応、インボイス制度や電子帳簿保存法の改正など、常に最新の知識と実務への適用が求められ、経理担当者には高度な専門性が要求されます。これにより、未経験者の育成には時間がかかり、既存社員の学習コストも増大しています。
1-3. 属人化の進行によるボトルネック
長年の慣習や業務の引き継ぎが不十分な場合、特定の担当者しかその業務の内容を把握していない「属人化」が発生しやすくなります。属人化は、担当者の退職や休職時に業務が滞るだけでなく、業務プロセス全体をブラックボックス化させ、効率化や改善の妨げとなります。新入社員のOJTも困難になり、人手不足に拍車をかけます。
1-4. デジタル化への対応遅れ
多くの企業でDX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれる中、経理部門では依然として紙ベースの作業や手入力が残っているケースが少なくありません。レガシーシステムからの脱却や新たなITツールの導入が遅れると、定型業務に多くの時間が割かれ、生産性向上の機会を逸してしまいます。これにより、本来集中すべき戦略的な業務にリソースを割けず、業務負荷が増大する原因となります。
2.人手不足が引き起こす経理部門の課題

人手不足は、単なる業務の遅延に留まらず、経理部門そして企業全体に深刻な影響を及ぼします。具体的にどのような課題が生まれるのかを見ていきましょう。
2-1. 業務負荷の増大とミスの発生リスク
人手不足の最も直接的な影響は、既存の経理担当者への業務負荷の集中です。限られた人数で多くの業務をこなそうとすれば、残業時間の増加や休日出勤が常態化し、結果として従業員の疲弊を招きます。疲弊は集中力の低下につながり、仕訳ミス、入力ミス、計算ミスといった経理処理におけるヒューマンエラーのリスクを増大させます。こうしたミスは、会社の社会的信頼を損なうだけでなく、税務調査での指摘や追加の納税に繋がる可能性もあります。
2-2. 従業員のモチベーション低下と離職率の上昇
過度な業務負荷は、従業員の心身の健康を損ない、仕事へのモチベーションを著しく低下させます。常に追われるような業務に忙殺されることで、スキルアップやキャリア形成のための時間も取れなくなり、達成感を感じにくくなります。このような状況が続けば、より良い労働条件を求めて離職を選ぶ従業員が増加し、さらなる人手不足を招く悪循環に陥る可能性が高まります。
2-3. 内部統制のリスク増大
経理業務は企業の資金を扱うため、厳格な内部統制が求められます。しかし、人手不足によって業務のチェック体制が手薄になったり、一人が複数の役割を兼務せざるを得なくなったりすると、不正や誤りを早期に発見する機会が失われます。これにより、横領や情報漏洩といったリスクが高まり、企業の信頼性やレピュテーションを大きく損なう事態に発展する可能性があります。
2-4. 経営判断への悪影響
経理部門は、企業の財務状況を正確に把握し、経営層にタイムリーな情報を提供する重要な役割を担っています。しかし、人手不足による業務の遅延やミスの発生は、月次決算や四半期決算の遅れ、財務諸表の信頼性低下に直結します。正確かつ迅速な情報が提供されなければ、経営層は的確な経営判断を下すことができず、事業戦略の遅れや機会損失に繋がりかねません。
3.人手不足解消の鍵!効率的な業務フロー構築の基本原則

経理部門の人手不足を根本的に解決するには、単に人員を補充するだけでなく、業務そのものを効率化し、少ないリソースで最大限の成果を出せる体制を構築することが不可欠です。ここでは、効率的な業務フロー構築のための基本原則を解説します。
3-1. 現状把握と課題の明確化
業務フロー改善の第一歩は、現状を正確に把握し、どこに問題があるのかを明確にすることです。
| 業務の洗い出し | 経理部門で行われているすべての業務をリストアップします。 |
| 工数の測定 | 各業務にどれくらいの時間とリソースが割かれているかを測定します。 |
| ボトルネックの特定 | 時間がかかりすぎている業務、ミスが発生しやすい業務、特定の担当者に集中している業務などを特定します。 |
| ヒアリング | 実際に業務を行っている担当者から、具体的な困りごとや改善点をヒアリングします。 |
このプロセスを通じて、漠然とした「人手不足」の原因を具体的な課題に落とし込むことが可能になります。
3-2. 業務の標準化とマニュアル化
属人化を解消し、誰でも一定の品質で業務を遂行できるようにするためには、業務の標準化とマニュアル化が不可欠です。
| 標準的な手順の確立 | 各業務のベストプラクティスを特定し、標準的な手順を定めます。 |
| マニュアルの作成・更新 | 標準化された手順を詳細なマニュアルとして文書化します。単なる手順書ではなく、判断基準や注意点、よくあるQ&Aなども盛り込むと良いでしょう。 |
| 共有と教育 | 作成したマニュアルは共有フォルダなどでアクセスしやすい状態にし、新入社員の教育や既存社員の知識共有に活用します。定期的な見直しと更新も重要です。 |
標準化とマニュアル化は、業務品質の均一化、教育コストの削減、そして業務引き継ぎの容易化に貢献します。
3-3. ITツールの積極的な活用
現代の業務効率化において、ITツールの活用は避けて通れません。
| 定型業務の自動化 | 入力作業、照合、集計など、繰り返し発生する定型業務はRPA(Robotic Process Automation)やマクロなどで自動化できないか検討します。 |
| クラウドシステムの導入 | 会計システム、経費精算システム、請求書発行システムなどをクラウド化することで、場所や時間にとらわれずに業務が可能になり、データ連携もスムーズになります。 |
| ペーパーレス化の推進 | 電子帳簿保存法に対応したシステムを導入し、紙の書類を削減することで、保管コストや検索時間を削減します。 |
ITツールは、人の手による作業を削減し、より付加価値の高い業務に集中できる環境を整えます。
3-4. 業務の優先順位付けと切り分け
すべての業務が等しく重要というわけではありません。業務の重要度と緊急度に応じて優先順位をつけ、不要な業務は廃止するか、外部に委託することを検討します。
| 重要度・緊急度マトリクス | 業務を「重要かつ緊急」「重要だが緊急ではない」「緊急だが重要ではない」「重要でも緊急でもない」の4象限に分類し、優先順位をつけます。 |
| ノンコア業務の特定 | 定型的なデータ入力、書類整理、郵送業務など、戦略性や専門性が低く、必ずしも自社の社員がやる必要のない業務(ノンコア業務)を特定します。これらの業務はアウトソーシングの有力な候補となります。 |
限られたリソースを最大限に活かすためには、どこに労力を集中させるべきかを明確にすることが重要です。
3-5. 属人化の解消
属人化は業務効率を阻害し、人手不足を悪化させる大きな要因です。
| 知識・ノウハウの共有 | 定期的な情報共有会や勉強会を実施し、個人の持つ知識やノウハウを組織全体で共有する文化を醸成します。 |
| 複数人による担当 | 重要な業務は複数人が担当できる体制を構築し、バックアッププランを準備します。 |
| 業務プロセスの可視化 | 業務フロー図や手順書を作成し、業務プロセス全体を「見える化」することで、誰でも業務内容を理解できるようにします。 |
属人化を解消することで、特定の担当者に依存することなく、柔軟で安定した経理部門を構築できます。
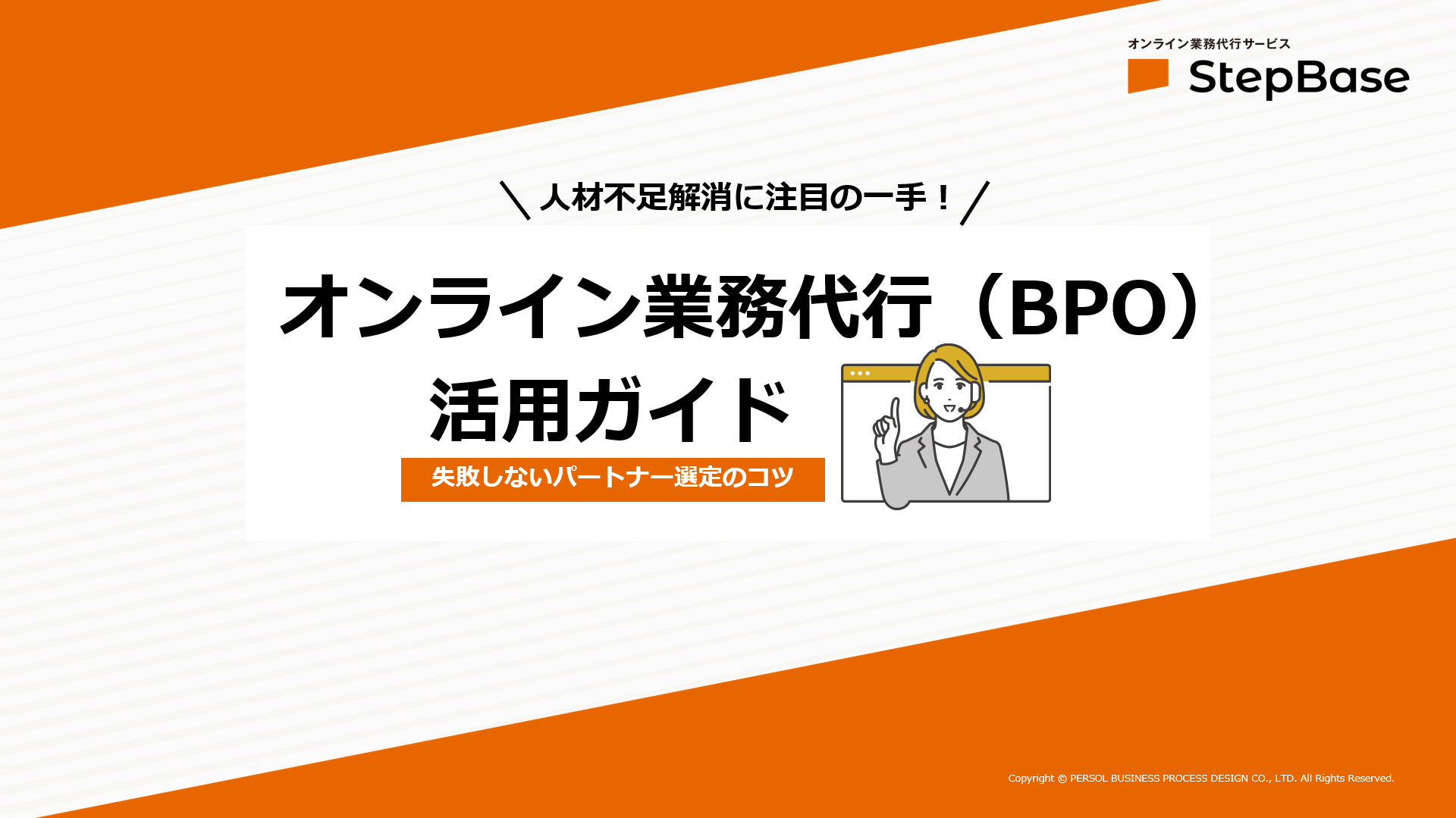
オンライン業務代行の活用ガイド~失敗しないパートナー選定のコツ~
| ・雑務でコア業務に集中できない… ・人材不足に採用難…教える余裕もない ・増加する業務に低コストで対応したい ・担当が急な休・退職で対応に困っている そのような課題の解決策として最近注目されるのが、「オンライン業務代行」です。特定の業務をオンラインで外部の専門企業に委託することで、コストを抑えて人材不足、業務効率化に対応できます。 本資料では、オンライン業務代行の基礎から活用法まで詳しく解説します。 ■本資料で分かること ・オンライン業務代行の導入メリット、活用法 ・失敗しないパートナー選定のコツ ・導入までの流れ、よくある質問&対応 |
4.具体的な業務フロー構築ステップ

ここからは、上記の基本原則を踏まえ、実際に効率的な業務フローを構築するための具体的なステップを解説します。
step1. 経理業務の棚卸しと可視化
まず、経理部門で行われているすべての業務を徹底的に洗い出します。
| 業務リストの作成 | 月次業務、年次業務、随時業務など、すべての業務項目を詳細に書き出します(例: 現金出納、預金管理、仕訳入力、請求書発行、経費精算、売掛金管理、買掛金管理、給与計算、固定資産管理、月次決算、年次決算、税務申告、監査対応など)。 |
| フロー図の作成 | 各業務について、「誰が」「いつ」「何を」「どのような手順で」「どのツールを使って」行い、「誰に引き継ぐか」を明確にしたフロー図を作成します。Excelや専用のツールを活用すると良いでしょう。 |
| 担当者・所要時間のヒアリング | 各担当者から、それぞれの業務にかかる時間や頻度、現在の課題点を具体的にヒアリングし、情報としてフロー図に加えます。 |
このステップで、経理部門の「現状」を客観的に把握し、業務プロセス全体を「見える化」することが目的です。
step2. 課題の特定と改善点の洗い出し
可視化された業務フローをもとに、非効率な点や改善すべき点を特定します。
| ボトルネックの発見 | 特定の担当者に業務が集中している箇所、承認プロセスに時間がかかっている箇所、手作業が多くミスが発生しやすい箇所などを特定します。 |
| 無駄な業務の特定 | 本当に必要なのか疑問な業務、重複している業務、過去の慣習で残っているだけの業務などを洗い出します。 |
| 属人化のチェック | 特定の担当者しかできない業務、マニュアルが存在しない業務を明確にします。 |
| IT化の可能性 | 手作業で行われている業務で、ITツールで自動化・効率化できるものがないかを検討します。 |
「なぜこの業務が必要なのか」「もっと良いやり方はないか」という視点で、一つ一つの業務を深く掘り下げて評価することが重要です。
step3. 新しい業務フローの設計と文書化
課題が明確になったら、改善策を盛り込んだ新しい業務フローを設計します。
| 業務の再設計 | 無駄な業務の廃止、プロセスの統合、担当者の再配置などを考慮し、効率的でシンプルかつミスが発生しにくい新しいフローを設計します。 |
| マニュアルの作成・更新 | 新しいフローに基づき、具体的な作業手順を詳細に記載したマニュアルを作成または更新します。誰が読んでも理解できる明確さが必要です。 |
| 役割分担の明確化 | 新しいフローにおける各担当者の役割と責任を明確に定義します。 |
| ITツール導入の検討 |
必要に応じて、どのITツールを導入し、どのように活用するかを具体的に計画に盛り込みます。 |
この段階では、理想的なフローを描くと同時に、実現可能性も考慮に入れる必要があります。
step4. ITツールの導入と活用
効率的な業務フローを実現するためには、適切なITツールの導入が不可欠です。
| クラウド会計システムの導入 | リアルタイムでのデータ連携、リモートでの業務遂行を可能にし、仕訳入力の自動化や決算早期化に貢献します。 |
| 経費精算システムの導入 | 従業員がスマートフォンから経費申請を行い、自動で仕訳が作成されることで、経費処理にかかる時間を大幅に削減します。 |
| 請求書発行・管理システムの導入 | 請求書の発行から送付、入金管理までをシステム化し、手作業によるミスをなくし、効率的な債権管理を実現します。 |
|
RPA(Robotic Process Automation) の活用 |
定型的なデータ入力、他システムへの転記、レポーティングなど、繰り返し発生する単純作業をロボットに任せることで、人間はより高度な業務に集中できます。 |
| AI-OCRの導入 | 領収書や請求書などの紙媒体の情報をAIが読み取り、データ化することで、手入力の手間とミスを削減します。 |
ITツールの選定にあたっては、自社の規模や予算、既存システムとの連携、サポート体制などを考慮し、費用対効果の高いものを選ぶことが重要です。
step5. アウトソーシングの検討
自社で行うべき業務と、外部に委託できる業務を切り分け、戦略的にアウトソーシングを活用します。
| ノンコア業務の特定 | 定型的な仕訳入力、経費精算チェック、給与計算、売掛金・買掛金管理など、専門性は高いが、必ずしも自社で行う必要のないノンコア業務を特定します。 |
| アウトソーシング先の選定 | 信頼できるアウトソーシングベンダーを選定します。実績、専門性、セキュリティ体制、対応範囲、費用などを比較検討し、自社のニーズに合ったパートナーを見つけます。 |
| 情報共有と連携体制の構築 | アウトソーシング後も、ベンダーとの密な情報共有や連携体制を構築し、スムーズな業務遂行を可能にします。 |
アウトソーシングは、経理部門のリソースを戦略的な業務に集中させ、人手不足を解消しながら業務品質を維持・向上させる強力な手段となります。
step6. 定期的な見直しと改善
業務フローは一度構築したら終わりではありません。時代の変化や会社の成長に合わせて、定期的に見直し、改善を続けることが重要です。
| 効果測定 | 新しい業務フロー導入後の効果(所要時間の短縮、ミスの削減、残業時間の減少など)を定期的に測定します。 |
| フィードバックの収集 | 実際に業務を行っている担当者から、改善点や課題に関するフィードバックを継続的に収集します。 |
| PDCAサイクルの実施 | 計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルを回し、常に最適な業務フローを目指します。 |
継続的な改善を通じて、経理部門は変化に強く、より効率的な組織へと進化していきます。
5.効率化をさらに加速させる!経理DX推進のポイント

経理部門の業務フロー効率化は、単なる改善に留まらず、DX(デジタルトランスフォーメーション)として推進することで、企業全体の生産性向上に貢献します。
5-1. RPAによる定型業務の自動化
RPAは、パソコン上で行われる定型的な操作(データ入力、クリック、コピペなど)を自動化するツールです。 経理では以下のような業務に活用できます。
| 仕訳データの入力・転記 | 複数のシステムからのデータ集計や会計システムへの入力。 |
| 支払業務 | 請求書の支払処理、銀行振込データの作成。 |
| レポート作成 | 月次・年次レポートのデータ抽出と加工。 |
| データ照合 | 銀行口座の入出金明細と会計データの照合。 |
RPAを導入することで、手作業によるミスをなくし、担当者はより判断が求められる業務に集中できるようになります。
5-2. クラウド会計システムの導入
クラウド会計システムは、インターネット経由で利用できる会計ソフトです。
| リアルタイムな情報共有 | 複数拠点やリモートワーク環境でもリアルタイムに会計データにアクセスでき、情報共有がスムーズになります。 |
| 自動連携機能 | 銀行口座やクレジットカード、POSレジなどと連携し、取引データを自動で取り込み、仕訳作成を効率化します。 |
| 自動仕訳機能 | 過去の仕訳パターンを学習し、自動で仕訳を提案することで、入力の手間を削減します。 |
| 決算業務の効率化 | 試算表や決算書が自動作成されるため、決算作業の早期化・効率化に貢献します。 |
クラウド会計は、経理業務の柔軟性と効率性を大幅に向上させる基盤となります。
5-3. AI-OCRによるデータ入力の効率化
AI-OCRは、AI技術を活用して紙の書類(領収書、請求書など)から文字情報を高精度で読み取り、データ化する技術です。
| 手入力作業の削減 | 領収書や請求書の情報をスキャンするだけで自動でデータ化され、手入力の手間が大幅に削減されます。 |
| 入力ミスの削減 | AIが高い精度で文字を認識するため、ヒューマンエラーによる入力ミスを防ぎます。 |
| ペーパーレス化の推進 | 紙の書類をデータ化することで、保管スペースの削減や検索性の向上に繋がります。 |
AI-OCRは、大量の紙媒体を扱う経理部門にとって、劇的な効率化をもたらす可能性を秘めています。
5-4. 経費精算システムの活用
経費精算システムは、従業員の経費申請から承認、精算、仕訳作成までの一連のプロセスを電子化するシステムです。
| 申請・承認プロセスの効率化 | 従業員はスマートフォンから領収書を撮影・アップロードし、オンラインで申請・承認が完結できます。これにより、申請者・承認者双方の手間が削減されます。 |
| 自動仕訳・会計連携 | 承認された経費データは自動で会計システムに連携され、仕訳が自動作成されるため、経理担当者の仕訳作業が効率化されます。 |
| 不正防止 |
不正な支出の自動アラート機能や定期区間の自動除外機能により、ガバナンス強化にも貢献します。 |
経費精算システムは、従業員と経理部門双方の業務負担を軽減し、生産性を向上させます。
6.アウトソーシングという選択肢

経理部門の人手不足解消と業務効率化において、アウトソーシングは非常に有効な戦略です。自社のリソースを最大限に活用しつつ、不足する部分を外部の専門家に委ねることで、多くのメリットを享受できます。
6-1. アウトソーシングのメリット・デメリット
✅メリット
| 人手不足の解消 | 採用・教育コストをかけずに、必要な時に必要なリソースを確保できます。 |
| 専門性の活用 | 経理のプロフェッショナルが業務を行うため、高品質なサービスが期待できます。法改正への対応も専門家が適切に行うため、情報収集や学習の手間を省けます。 |
| コア業務への集中 | 定型業務やノンコア業務を外部に委託することで、自社社員はより付加価値の高いコア業務に集中できます。 |
| コスト削減 | 自社で正社員を雇用するよりも、トータルコストを削減できる場合があります。 |
| 内部統制の強化 | 外部の目でチェックが入ることで、内部統制の強化にも繋がります。 |
| 属人化の防止 | 業務の引き継ぎやマニュアル化が進み、属人化のリスクを軽減できます。 |
✅デメリット
| ノウハウの蓄積の停滞 | 外部委託する業務に関する社内ノウハウが蓄積されにくくなる可能性があります。 |
| 情報漏洩のリスク | 委託先との情報共有が必要なため、セキュリティ対策が重要です。 |
| コミュニケーションコスト | 外部との連携にはコミュニケーションコストが発生します。 |
| 委託費用 | サービス内容によってはコストが高くなることもあります。 |
6-2. どんな業務をアウトソーシングできるのか
経理業務の中でも、以下のような業務はアウトソーシングに適しています。
| 日常の記帳業務 | 仕訳入力、伝票整理、会計ソフトへの入力など。 |
| 経費精算業務 | 従業員の経費申請チェック、精算処理。 |
| 給与計算業務 | 給与計算、社会保険手続き、年末調整など。 |
| 売掛金・買掛金管理 | 請求書発行、入金確認、支払い処理。 |
| 月次・年次決算補助 | 決算資料作成のサポート。 |
| 税務申告補助 | 法人税、消費税などの申告書類作成補助。 |
これらの業務を外部に委託することで、経理部門の負担を大幅に軽減し、戦略的な業務に集中できる環境を整えることができます。
6-3. アウトソーシング先選定のポイント
| 実績と専門性 | 経理業務に関する豊富な実績と専門知識を持つ業者を選びましょう。 |
| セキュリティ体制 | 機密情報を扱うため、情報セキュリティ対策が万全な業者を選定することが不可欠です。 |
| 対応範囲と柔軟性 | 自社のニーズに合わせた業務範囲に対応できるか、柔軟な対応が可能かを確認します。 |
| コミュニケーション | 担当者とのコミュニケーションが円滑に行えるか、報告体制は明確かを確認します。 |
| 費用対効果 | サービス内容と費用が見合っているか、長期的な視点でコストメリットがあるかを検討します。 |
まとめ:効率的な業務フローで持続可能な経理部門へ
経理部門の人手不足は、企業経営にとって避けては通れない喫緊の課題です。しかし、この課題は単に人員を増やすだけでなく、業務フローを根本から見直し、効率化を図ることで、持続可能で生産性の高い経理部門へと変革するチャンスでもあります。
本記事で解説したように、まずは現状の業務を可視化し、課題を明確にすることから始めましょう。そして、業務の標準化、ITツールの積極的な活用、属人化の解消、そして戦略的なアウトソーシングの導入を通じて、非効率な業務プロセスを刷新してください。特に、クラウド会計システム、経費精算システム、RPA、AI-OCRなどのDX推進は、経理業務の生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。
これらの取り組みは、経理部門の負担を軽減し、ミスの削減、コストの最適化、そして何よりも従業員がより創造的で付加価値の高い業務に集中できる環境を整えます。結果として、企業の経営判断を支える正確かつタイムリーな情報提供が可能となり、企業全体の競争力強化に貢献するでしょう。
StepBaseは、経理業務の効率化やDX推進、そして最適なアウトソーシング戦略の立案・実行をサポートいたします。経理部門が抱える課題を深く理解し、オーダーメイドのソリューションを提供することで、人手不足を解消し、持続的な成長を実現するための支援をいたします。経理部門の課題解決に向けて、まずはお気軽にご相談ください。
▼ StepBase経理のサービス詳細はこちらから
https://step-base.jp/accounting/
事務業務の人材不足・業務効率化にお悩みなら
「StepBase」にご相談ください!
|
パーソルグループの
|
✔ 経験豊富なプロが業務を代行 ✔ 10時間/3.9万円からスタートできる ✔ 採用するより素早く、人材不足解消! |