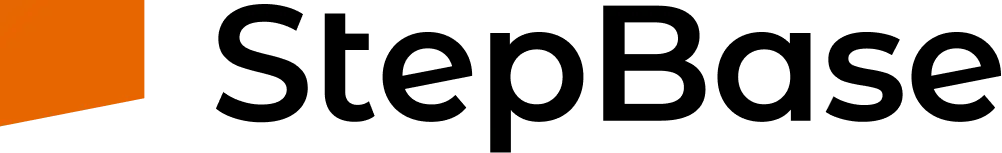内定辞退を防ぐ!候補者体験を向上させる面接官のコミュニケーション術と育成法

競争激化の採用市場で「面接官」の役割が変化している
少子高齢化による労働人口の減少が深刻化する中、採用市場は「売り手市場」が続いています。企業は優秀な人材を確保するため、もはや「企業が候補者を選ぶ」という一方的な姿勢ではなく、「候補者から選ばれる企業」となることが不可欠です。
この激化する人材獲得競争において、内定辞退を防ぎ、候補者の入社意欲を最大限に高めるために最も重要な要素の一つが「候補者体験(Candidate Experience:採用CX)」です。そして、その採用CXを左右する上で、面接官の果たす役割は極めて大きいと言えます。
面接官は単に応募者のスキルや経験を見極めるだけでなく、企業の「顔」としてブランドイメージを伝え、候補者の入社意欲を動機づける重要な役割を担っています。面接官の印象が直接的に企業のイメージに繋がり、候補者の「この会社で働きたい」という気持ちを育むかどうかに大きく影響するため、面接官のコミュニケーションスキルと育成は、採用成功の鍵を握ると言っても過言ではありません。
本記事では、内定辞退を防ぎ、候補者体験を向上させるための面接官に求められるコミュニケーション術と、その面接官を育成するための具体的な方法について、詳しく解説します。
【関連記事】面接評価シート 作り方:職種別・段階別で成果を出すカスタマイズ術とテンプレート
【関連記事】採用効率化と応募者体験向上で採用率UP!内定辞退を防ぐコミュニケーション術
目次
1. 採用CX(候補者体験)が内定辞退を防ぐ鍵となる理由

1-1. 「選ばれる企業」になるための採用CXの重要性
現代の採用市場では、優秀な人材ほど複数の企業から内定を得る傾向にあります。そのため、企業は「選ばれる」ための努力を惜しんではなりません。採用CXを向上させることは、候補者の自社に対する志望度を高め、競合他社ではなく自社を選んでもらうための強力な差別化要因となります。
1-2. 採用CX向上がもたらす具体的なメリット
採用CXを重視し、改善することで、企業は以下のような多岐にわたるメリットを享受できます。
| 候補者の志望度向上と歩留まり改善 | 選考プロセス全体を通して良い体験を提供することで、候補者の入社意欲が高まり、応募率の増加や内定辞退の抑制に直結します。 |
| ポジティブな企業イメージの形成 | 面接官の対応や選考プロセス全体を通じて良い印象を持った候補者は、たとえ入社に至らなくても、企業のファンとなり、良い口コミを広めてくれる可能性があります。 |
| 将来的なタレントプールの構築 | 良い選考体験は再応募に繋がりやすく、一度は縁がなくても将来的に再び候補となり得る人材(タレントプール)の蓄積に貢献します。 |
| 入社後のエンゲージメント向上 | 採用前から企業に良い印象と愛着を持った状態で入社することで、入社後の定着率や活躍に繋がりやすくなります。 |
1-3. 採用CXを疎かにするリスク
一方で、採用CXを疎かにすると、企業にとって大きなリスクとなり得ます。
| 応募数の減少と内定辞退の増加 | 競合他社に比べて魅力が伝わらなければ、応募者が減少したり、選考途中で辞退したりする可能性が高まります。 |
| ネガティブな企業イメージの拡散 | 悪い選考体験はSNSや口コミサイトを通じて瞬く間に広がり、企業の評判を著しく損ねる恐れがあります。 |
面接官は、これらの採用CXの各タッチポイントにおいて、企業の「顔」として候補者と直接接する最前線の存在です。面接官の質が採用CXを大きく左右することを理解し、その育成に注力することが、採用成功の必須条件と言えるでしょう。
2. 内定辞退に直結する面接官の「NG行動」と「スキル不足」

2-1. 評価基準の不明確さ・属人化
面接官の主観に頼った評価は、選考の公平性を損ない、採用のミスマッチを引き起こす原因となります。
| 統一された評価基準の欠如 | 面接官間で評価の目線が揃っていないと、同じ能力を持つ候補者でも評価が分かれてしまい、優秀な人材を見逃したり、不適切な人材を採用したりする可能性があります。 |
| 求める人物像の共有不足 | 自社がどのような人材を求めているのかが面接官間で明確に共有されていないと、見極めの精度が低下し、入社後に「こんなはずではなかった」というミスマッチに繋がりかねません。 |
2-2. 不適切なコミュニケーション
面接官のコミュニケーション不足や不適切な言動は、候補者に企業への不信感を与え、志望度を著しく低下させます。
| 一方的な質問攻め | 候補者の話を聞かず、一方的に質問を浴びせるだけでは、会話のキャッチボールができず、候補者は「話を聞いてくれない会社」という印象を抱きます。 |
| 不適切な質問 | 思想信条、家族構成、出身地など、就職差別につながる質問や、プライベートに過度に踏み込む質問は、コンプライアンス違反であり、候補者に不快感を与える最たる行為です。 |
| 企業の魅力を伝えきれない | 候補者の入社意欲を高めるためには、自社のビジョンや働きがい、社員の魅力を積極的に伝える必要があります。これらを漠然としか伝えられない面接官は、候補者の心を掴むことができません。 |
| 態度や表情の悪さ | 腕組み、無表情、履歴書ばかりを見るなどの態度は、候補者に威圧感や不信感を与え、企業全体のイメージを悪化させます。 |
| レスポンスの遅延 | 書類選考の合否連絡や面接日程調整、内定通知などの連絡が遅いと、候補者は「自社への関心が低い」と感じ、他社へ流れてしまう可能性が高まります。 |
2-3. 面接準備の不足
面接官が事前の準備を怠ることも、候補者体験を損ねる要因となります。
| 履歴書や職務経歴書の読み込み不足 | 候補者の情報を事前に把握していないと、トンチンカンな質問をしたり、候補者がすでに記載している内容を再度尋ねたりすることになり、候補者は「自分に関心がない」と感じてしまいます。 |
| 面接官間の情報共有不足 | 複数の面接官が候補者に同じ質問を繰り返したり、評価基準が共有されていなかったりすると、候補者は不信感を抱きます。 |
これらのNG行動やスキル不足は、直接的に候補者の志望度を低下させ、内定辞退へと繋がります。面接官一人ひとりが、自身の役割と影響力を自覚し、改善に向けた努力をすることが求められます。
3. 候補者の心を掴む!面接官に求められる「コミュニケーション術」

面接官は、候補者にとって企業の顔であり、採用活動の成否を分ける重要な存在です。内定辞退を防ぎ、候補者の入社意欲を高めるためには、以下のコミュニケーションスキルを磨く必要があります。
【関連記事】採用効率化と応募者体験向上で採用率UP!内定辞退を防ぐコミュニケーション術
3-1. 好印象を与える「印象力」
第一印象は面接の成否を大きく左右します。候補者に「この会社で働いてみたい」と思わせるための印象力を意識しましょう。
| 笑顔と明るい挨拶 | 緊張している候補者をリラックスさせるため、まずは笑顔で迎え入れ、明るい声で挨拶しましょう。「緊張されていますか?」「リラックスしてくださいね」といった声かけも有効です。 |
| 清潔感のある身だしなみ | 面接官の身だしなみは、企業のイメージに直結します。清潔感のある服装や髪型を心がけましょう。 |
| 傾聴と共感の姿勢 | 候補者の話に真剣に耳を傾け、頷きやアイコンタクトで共感を示すことで、候補者は安心して話すことができます。履歴書と候補者の顔を頻繁に見比べる行為は避け、目の前の候補者に集中しましょう。 |
3-2. 本質を見極める「質問力」と「情報収集力」
限られた時間で候補者の本質や潜在能力を見抜くためには、質の高い質問と情報収集力が不可欠です。
| オープンエンドな質問で本音を引き出す | 「なぜ?」「どのように?」「具体的には?」といったオープンエンドな質問を投げかけることで、候補者の思考プロセスや価値観、行動特性を深く引き出せます。 |
| 掘り下げ質問で深掘りする | 候補者の回答に対し、「それは具体的にどのような状況でしたか?」「その時、あなたは何を考え、どう行動しましたか?」など、5W1Hを意識した質問で深掘りすることで、具体的な経験やスキルを把握できます。 |
| 自社にフィットする人材を見極める質問 | 自社の企業文化や求める人物像に照らし合わせ、「どのような働き方をしたいか」「チームでの協調性」など、スキルだけでなくパーソナリティや価値観に触れる質問をすることで、ミスマッチを防ぎます。 |
| タブー質問の理解と回避 | 法律や倫理に反する質問(家族構成、思想信条、本籍地など)は絶対に避けましょう。面接官として何を聞いてはいけないかを正しく理解していることが重要です。 |
3-3. 入社意欲を高める「惹きつけ力」
候補者に「この会社に入社したい」と思わせるための、自社の魅力を効果的に伝えるスキルです。
| 企業のビジョン・ミッションの明確な伝達 | 経営理念やビジョンを自身の言葉で語り、候補者が共感できるようなストーリーを交えることで、入社後のキャリアパスや貢献イメージを具体的に描かせることができます。 |
| 具体的な成功事例や社員のエピソード | 抽象的な説明だけでなく、「実際にこんなプロジェクトでこんな成功体験がある」「〇〇さんはこんな成長を遂げた」といった具体的な事例や社員の魅力的なエピソードを話すことで、リアリティを持って自社の魅力を伝えられます。 |
| 候補者のキャリアビジョンとの接続 | 候補者の話から得た情報をもとに、自社で働くことが、その候補者のキャリアプランや目標達成にどう繋がるかを具体的に示すことで、入社後のイメージをポジティブに膨らませることができます。 |
| 建設的なフィードバック | 候補者の質問や疑問に対して、丁寧かつ誠実に回答するだけでなく、面接の最後に「今日の面接で〇〇さんの△△という点が印象に残りました」など、ポジティブなフィードバックを与えることで、候補者は「きちんと自分を見てくれている」と感じ、企業への好感度を高めます。 |
これらのコミュニケーション術を意識的に実践することで、面接は単なる評価の場から、候補者と企業が互いを理解し、信頼関係を築く「動機付けの場」へと昇華させることができます。
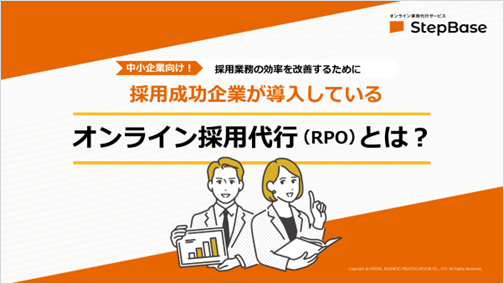
成功企業が導入している採用代行(RPO)とは?
|
・採用業務の人材不足で対応遅れ・辞退が発生 |
4. 成果を出す面接官を「育成」するための具体的な方法

面接官のスキルアップは、一朝一夕には成りません。体系的な「面接官育成」プログラムを導入し、継続的に取り組むことが、内定辞退防止と採用成功に繋がります。
4-1. 面接官育成の重要性
ある調査によると、採用が成功している企業の65%が面接官トレーニングを実施しているのに対し、採用に課題を感じる企業の70%以上が実施していないことが明らかになっています。このデータは、面接官育成が採用成功に不可欠であることを強く示唆しています。
( https://www.manpowergroup.jp/client/manpowerclip/employ/interviewer-training.html )
面接官トレーニングには、以下のような効果が期待できます。
| 採用精度の向上とミスマッチ防止 | 評価基準の標準化により、面接官ごとの評価のバラつきを抑え、自社に最適な人材を見極める精度が高まります。 |
| 内定辞退の抑制 | 面接官の魅力訴求力が高まることで、候補者の志望度を向上させ、他社への内定辞退を防ぎます。 |
| 企業イメージの向上 | 面接官のコミュニケーションスキルが向上することで、候補者に良い印象を与え、企業全体のブランディングに貢献します。 |
4-2. トレーニング導入前の準備
効果的な面接官育成のためには、事前の準備が重要です。
| 採用課題の整理と共有 | まず、自社の採用活動における具体的な課題(例:内定辞退率が高い、早期離職が多い、特定の部署で求める人材が集まらないなど)を明確にし、採用チーム内で共有します。課題が明確でなければ、トレーニングの目的も曖昧になり、効果が半減してしまいます。 |
| 求める人物像・評価基準の明確化 | どのようなスキル、経験、人物像を求めているのかを具体的に言語化し、面接官全員で共有します。評価項目と基準を詳細に設定することで、面接官間の評価のブレを防ぎ、客観的な判断を可能にします。 |
| 面接官マニュアルの作成と配布 | 面接の基本的な流れ、評価基準、質問例、NG行動、企業の魅力付けのポイントなどをまとめたマニュアルを作成し、面接官全員に配布します。これにより、面接の質を一定に保ち、コンプライアンス遵守を徹底できます。 |
4-3. 具体的な面接官育成プログラム
準備が整ったら、以下の手法を組み合わせた育成プログラムを実施しましょう。
✅step1. 座学研修による基礎知識の習得
面接官として必要な基礎知識を体系的に学びます。
| 面接官の役割と心構え | 面接が単なる見極めの場ではなく、企業の代表として候補者を動機づける場であることを理解させます。 |
| 採用市場の現状と採用CXの重要性 | 売り手市場の背景や、採用CXが内定辞退防止に果たす役割を共有し、面接官の意識改革を促します。 |
| コンプライアンス(法規遵守) | 面接で聞いてはいけない質問や、個人情報の取り扱いなど、法律や倫理に関わる基本知識を徹底します。 |
| 質問力・傾聴力の基礎 | 効果的な質問の仕方(オープンエンド質問、掘り下げ質問など)や、アクティブリスニングの重要性、相槌の打ち方などを学びます。 |
| 魅力訴求のポイント | 自社のビジョン、文化、働きがいを効果的に伝えるためのストーリーテリングや具体的なエピソードの活用法を習得します。 |
✅step2. ロールプレイング・模擬面接による実践演習
座学で得た知識を実践に移すための重要なステップです。
| 模擬面接の実施 | 面接官役と候補者役に分かれて模擬面接を行います。アイスブレイクから質問、魅力付け、逆質問まで、一連の流れを体験します。 |
| フィードバックと改善 | 模擬面接後、参加者同士や講師からの客観的なフィードバックを受け、自身の改善点や強みを認識します。具体的な言葉遣いや表情、質問の仕方など、細部にわたる改善に繋げます。 |
| メンターシップ | 経験豊富なベテラン面接官が、若手面接官のメンターとなり、OJT形式で指導します。実際の面接に同席し、終了後にフィードバックを行うことで、自社の文化に即した実践的なスキルを習得できます。 |
✅step3. 外部研修・セミナーの活用
自社だけでは難しい専門的な知識や、他社の事例を学ぶ機会を提供します。
| 専門機関の研修 | 人事・採用コンサルティング会社などが提供する面接官トレーニングプログラムに参加することで、体系的かつ効率的にスキルを習得できます。 |
| 最新情報のインプット | 採用トレンドや候補者の動向など、常に変化する市場の最新情報を得ることで、面接官としての知識をアップデートできます。 |
✅step4. 継続的な改善と運用
面接官育成は一度行えば終わりではありません。継続的なPDCAサイクルを回すことが重要です。
| 候補者アンケートの実施 | 選考を受けた候補者に対して、面接体験に関するアンケートを実施し、率直なフィードバックを収集します。辞退者には辞退理由をヒアリングすることで、面接プロセスの課題を浮き彫りにできます。 |
| 面接官間の評価すり合わせ | 面接後には、面接官同士で評価の食い違いがないかを確認し、意見交換を行います。必要に応じて評価基準や質問内容を見直すことで、統一された目線を維持します。 |
| 定期的なブラッシュアップ | 社会情勢や求職者のニーズは常に変化しています。トレーニング内容も定期的に見直し、最新の情報やトレンドを反映させることで、常に効果的な面接官育成を目指します。 |
5. 面接官育成の成功事例と効果的な運用

5-1. データに基づいた採用プロセスの改善
Googleのような先進企業は、データ分析を積極的に活用し、面接の評価基準を標準化しています。複数の面接官が共通の評価シートやスコアカードを用いることで、客観的かつ公平な評価を実現し、採用の精度を高めています。過去の採用データを分析し、成功パターンを特定することで、どのような面接官が、どのようなコミュニケーションを通じて優秀な人材を獲得できているかを可視化し、育成に活かすことができます。
5-2. 文化フィット重視の採用と面接官の役割
Zapposなどの企業では、スキルや経験だけでなく、企業文化への適合性を重視した採用を行っています。面接官は、自社の価値観や理念を深く理解し、候補者がそれにフィットするかを見極めるだけでなく、自社の文化の魅力を伝える役割も担います。面接官が「自社の良さ」を自分自身の言葉で語れるようになる育成が重要です。
5-3. 継続的なフィードバックと改善サイクル
メルカリでは、事業拡大に伴う面接官の技量のバラつきが課題となり、採用プロセスの体系化と情報共有に力を入れました。さらに「候補者アンケート」を実施し、候補者からの選考活動に関するフィードバックを収集。この意見を面接官の育成に反映させ、担当者のスキルアップに繋げています。このように、候補者からの生の声を取り入れ、改善に活かすサイクルは、面接官育成の質を高める上で非常に有効です。
面接官育成は、採用活動の課題解決に留まらず、入社後の従業員の定着や活躍、ひいては企業全体の成長に貢献する戦略的な投資であると言えるでしょう。
まとめ
人材獲得競争が激化する現代において、内定辞退を防ぎ、企業が持続的に成長するためには、候補者体験の向上が不可欠です。そして、その採用CXを左右する重要な鍵を握るのが「面接官」の存在です。
面接官は、単なる評価者ではなく、企業の「顔」として候補者に好印象を与え、入社意欲を高める「動機付け」の役割を担っています。好印象を与える「印象力」、候補者の本質を見極める「質問力」と「情報収集力」、そして自社の魅力を効果的に伝える「惹きつけ力」といったコミュニケーションスキルを磨くことは、採用成功に直結します。
これらのスキルを面接官一人ひとりが習得し、実践するためには、体系的かつ継続的な「面接官育成」が不可欠です。座学研修で基礎知識を学び、ロールプレイングで実践力を養い、候補者からのフィードバックを通じて常に改善を続けるPDCAサイクルを回すことで、成果を出す面接官集団を育成できます。
求める優秀な人材を確実に獲得し、内定辞退の壁を乗り越えるためには、面接官のコミュニケーション術の向上と戦略的な育成が、今、最も重要な採用戦略の一つです。
採用活動について悩みがある方や、長期的な採用支援が必要な方は、ぜひStepBaseにご相談ください。
StepBase採用は幅広い採用業務に対応可能で、採用ノウハウを自社で蓄積できるサポートも提供しています。
▼ StepBase採用のサービス詳細はこちらから
https://step-base.jp/recruitment/
採用業務の人材不足・業務効率化にお悩みなら
「StepBase」にご相談ください!
|
パーソルグループの
|
✔ 採用業務の経験豊富なプロが業務代行 ✔ 10時間/3.9万円からスタートできる ✔ 応募者対応やスカウト配信もお任せ |